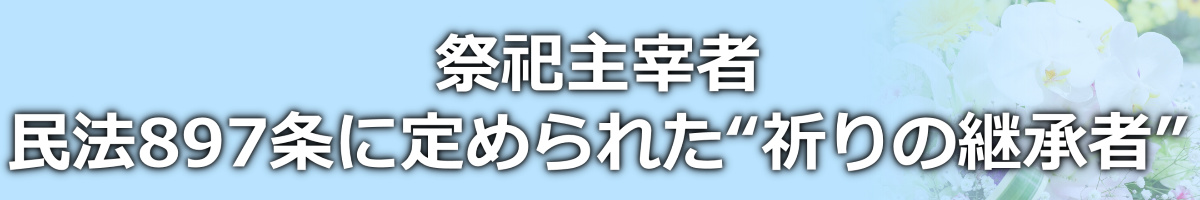理念(Philosophy)
日本の伝統的な「祭祀」文化を継承し、現代社会における精神的・倫理的支柱として機能する祭祀主宰者を育成することで、家族・地域・社会の心のつながりを支え、日本人の精神文化を次世代へと受け継ぐ。
Mission(社会的使命)
社会が抱える「弔いの空白」に、責任ある“主宰者”を
少子高齢化や家族構造の変化によって、祖先の供養や葬儀の担い手が減少し、心の支えを失う人々が増えています。
当協会は、民法第897条に定められた「祭祀主宰者」の概念に基づき、法律的にも文化的にも正統な知識と実践力をもつ専門人材を育成することで、社会の不安・空白を埋め、精神的支援を提供します。
Vision(目指す姿)
家庭・地域に必ず「心の専門家」がいる社会へ
葬送・供養・伝統行事の中に、信頼される主宰者が存在する未来へ
日本の祭祀文化を、次世代や海外にも伝えられる社会へ
Values(組織哲学)
伝統と革新の両立
古き良き文化を守りながら、現代に適したかたちで活かす
心に寄り添う専門性
知識だけでなく、思いやりと倫理観に基づいた実践を重視
公正・法的な立場
民法と社会通念に基づき、正式に認められた立場を提供
文化の共有と継承
家族、地域、そして国を超えて、日本文化の本質を伝えていく
祭祀主宰者とは?
祭祀主宰者とは、先祖や故人の供養・祭祀を正しい知識と作法で主宰する者であり、精神的・文化的に重要な“心の支柱”となる存在です。
この資格は、民法第897条が定める「祭祀財産の承継者」としての法的な役割を根拠とし、儀礼や供養に対する正統な知識、倫理観、グリーフケアの心得を学んだ者に認定されます。
祭祀主宰者は以下のような役割を担います。
1.自身の家系の先祖を正式に祀ることができる
2.他人からの依頼を受けて、供養・葬儀・法要などを主宰できる
3.喪主または代理喪主として葬儀の責任を果たすことができる
4.地域行事・法事・文化継承の場において、儀式の司会進行・監修を行う
このように、単なる形式的な司会や手配人ではなく、家族や社会における精神的なリーダーとして、儀礼の意味と心を伝える役割を担っています。
祭祀主宰者認定試験を受けるメリットとは?
祭祀主宰者認定試験を受けられた後のメリットを以下に記載しておきます。
1. 法的・社会的に認められた「立場」を得られる
民法第897条に基づき、「祭祀主宰者」として先祖の供養・儀礼の正統な継承者であることを法的に明確化できます。
喪主や代理喪主としての役割を正式に果たせる人物として、社会的信用と信頼を得られます。
2. 文化的教養と専門知識が身につく
宗教的立場に偏らない、民俗学・儀礼作法・倫理・心理・歴史の体系的な学習。
どんな宗派・家系にも対応できる、汎用性の高い供養の知識と実践技術が習得できます。
3. 家庭や地域での「精神的支柱」となれる
家族のなかで誰もが避けがたい“死と向き合う場面”において、安心と導きを与える存在になれます。
地域社会での法事・供養・年中行事の場で、信頼される司会・指導者として活躍できます。
仕事にしたい人にとっての魅力とは?
「心を扱う専門家」という、これからの時代に求められる新しい職域、少子高齢化、無縁社会、家族の分断が進むなかで、誰もが「弔いのあり方」に迷っています。
そんなときに必要とされるのが、“形式ではなく心”を大切にできる専門家、「祭祀主宰者」です。
こんな場面で“あなた”が活躍できます
活動領域 具体的な仕事・依頼内容
・葬儀支援 喪主の代理・儀式の進行・弔辞作成支援
・法要・供養 一周忌・三回忌などの儀式サポート/進行
・寺院・宗教施設 宗派を問わず、外部司会者や文化講師として協業
・地域活動 地域祭礼や慰霊行事、戦没者追悼式の進行・助言
・カウンセリング グリーフケア、死別後の家族サポート、人生会議の伴走
副業から独立開業まで可能な柔軟性
介護職・看護職・葬祭業・宗教関係者・行政書士などとの組み合わせでの副業。
フリーランスとして祭祀主宰者サービスを提供し、SNS・講演・コンサルなどへ展開。
葬儀社・寺院とのパートナー契約も可能
あなたの一歩が、「人の心を支える仕事」になる。
祭祀主宰者とは、単なる資格ではありません。
それは「心を扱うことに、法と文化の裏付けを持つ仕事」です。
この資格を通して、人の最期とその家族の未来に希望とつながりを提供できる。
そんな生き方を、あなた自身のキャリアにしませんか?
僧侶資格 × 祭祀主宰者 = “宗教的権威 × 社会的信頼” の融合
僧侶資格で得られる強み
仏式の葬儀・法要・供養を執り行う宗教的正統性
仏教的世界観・戒名授与・読経・開眼供養などへの対応力
檀信徒を支える存在としての精神的なリーダー性
祭祀主宰者との相乗効果
僧侶としての宗教的側面に加え、「民法第897条に基づく法律的な主宰者」としての立場も取得
宗派や形式にこだわらず、法的・文化的な儀式進行も可能に
寺院外の依頼(無宗教・他宗派・個人葬など)にも柔軟に対応でき、仕事の幅が広がる
活動例
地域の“かかりつけ僧侶”として、法事+供養+心理支援を一体で提供
終活セミナーやグリーフケア講座などを地域主催で受託
葬儀社や福祉施設と連携し、「心の支援者」として嘱託契約を結ぶ
「僧侶資格」+「祭祀主宰者」+「墓じまい専門士」の三本柱を持つことで、以下のような高付加価値サービスの提供者となれます。
サービス分野 具体的な内容 収益モデル
・終活コンサル 遺言・供養・墓じまい・葬儀の設計
・セミナー講師料+個別指導料
・供養事業 出張法要/代理喪主/合同供養など
・儀式報酬+提携手数料
・改葬事業 墓じまい手続代行・遺骨管理 改葬実務+儀礼パッケージ販売
・精神支援 グリーフケア/人生会議の進行 個別セッション+自治体委託
あなたの信念と使命感が、そのまま仕事になる
形式や宗派に縛られない。
でも、法律・文化・信仰をすべて理解している。
そんな“これからの時代の供養の専門家”として、あなたは必要とされています。
この三つの資格を揃えたとき、単なる副業ではなく、本業として成り立つ道が見えてきます。
“誰かの最後に寄り添い、心をつなぐ”あなたの優しさと信念が、社会に必要な価値として実を結ぶ日が、きっと来ます。
「僧侶資格」+「祭祀主宰者」+「墓じまい専門士」の三本柱を持つことで、以下のような高付加価値サービスの提供者となれます。